以前から気になってはいたのですが、Parallels Desktopを試してみました。
今回使ってみたのは最新のParallels Desktop19です。

僕の用途としてはおもにアプリ開発の検証用です。
通常は母艦のMacBookで開発してるのですが、何かの拍子に環境が壊れて修復が面倒なことになることがあります。
そこで開発環境のツールのアップデートとかの時には事前に検証したり、いろいろ試せて壊れても問題ない環境があると便利なのでParalles Desktopを試してみました。
また、Paralles DesktopというとOSにWindowsを導入するブログはよくみるのですが、この記事ではMacOSも試してます。

Parallels Desktopについて
Parallels Desktopは、Mac上でWindowsや他のオペレーティングシステムを仮想的に実行することができるソフトウェアです。これにより、ユーザーは再起動せずにMacOSとWindowsを同時に使用することが可能になります。
また、仮想環境を使えば母艦の環境を壊すことなく、新しいツールやアップデートを安全にテストすることができます。
競合する仮想化ソフトウェア
Parallels Desktopと同じような機能を持つ他の仮想化ソフトウェアも存在します。
各ソフトウェアはそれぞれに特性と長所、短所を持っています。それぞれのニーズに合わせて選択することが重要ですが、Apple SiliconのMacで使うなら実質Parallels Desktop一択の状況です。
Parallels Desktopを試す理由
通常、私はMacBookを使用して開発を行っています。しかしながら、何かの拍子に開発環境が壊れてしまうと修復が大変なことがあります。そんな時、Parallels Desktopが便利そうです。
Parallels Desktopを導入することで、開発環境のツールのアップデートなどを行う際に事前に検証することが可能になります。また、何かを試して環境が壊れてしまっても仮想環境なので母艦には問題ありません。

このソフトウェアを使用することで、Macユーザーは再起動せずにMacOSとWindowsを同時に使用することが可能になります。これは、開発の効率向上が期待できそうです。
Windowsを仮想環境で試してみる
Parallels DesktopでWindowsの仮想環境を作るのは驚くほど簡単です。
Parallels Desktopをインストールしたらほんの数クリックで仮想環境自体はできてMac上でWindowsが動いてしまいます。
ただ、Apple SiliconのMacで構築できるのは通常のIntelのPCで使われているx86アーキテクチャのWindowsではなく、ARM版のWindowsになります。
全てのWindowsアプリケーションがARM版のWindowsで動作するわけではないため、互換性の問題がある場合があります。それでも、Parallels Desktopを利用することで、WindowsをApple SiliconのMacで使うことが可能になるのは便利です。

ちなみにARM版Windowsのライセンスと通常のWindowsのライセンスは区別がないようで、通常盤のライセンスがあれば使えるようです。
ライセンスを持ってなくても試用はできますが、多分そのうちライセンス認証で使えなくなると思います。
とりあえず、UnityやVS Code、Git関連のツールなど僕が普段使用している開発ツールを使ってみましたがちゃんと動作しました。
ちなみに僕が気に入っているタイピング練習用のアプリでゾンビ打というかなり古いゲームがあるのですが、これもちゃんと動作しました。

10年以上やってるよね。よくも飽きずに。

これはSEGAの迷作。もう買えないけど。
このゲーム、Surface Pro 9では正常に動かずにガッカリしていたのですが、MacBookのしかも仮想環境でまた遊べるようになったのは驚きです。ちなみにAMD版のThinkPadでは動作してました。
それと、ちょうど最近、M1のMacBook AirからM3のMacBook Airに買い替えをしたところなのですが、M1ではときどきゲームのパフォーマンスが落ちることがあったのが、M3ではそういうこともなくプレイできました。
まぁ、古いゲームなのでそれほどマシンスペックを要求されるゲームではないのですが。
全体的には仮想環境でもちゃんと動く感じでした。
リモートデスクトップとかを使ってリモートでWindowsを使うよりは、十分快適に動いてる気がします。
MacOSを仮装環境で試してみる
MacOSの方も同様に数クリックで仮想環境自体はできてしまいます。
こちらでもUnityやVS Code、Git関連のツールなど僕が普段使用している開発ツールを使ってみましたがちゃんと動作しましたし、パフォーマンス的にも問題なく十分使えそうです。
ただ、問題点がいくつかありました。
Apple IDが使えないのは結構困るかもしれないです。MacOSへのログイン時もそうですし、iCloudやAppStoreへのログインもできないので普段使っているアプリが使えません。
どうもApple IDが使えないのはApple側の問題のようでParallels Desktop側で解決できる問題ではないようです。今後も解決しないかもしれないですね。
キーボードは、僕のMacBookはJIS配列なのですがUS配列と認識されてしまいます。キーボード設定アシスタントがなぜか使えなそうだったので設定変更もできず地味に不便です。
マウスのホイールのスクロール向きも逆になるのも地味にストレスです。トラックパッドも含めて全体の設定を逆にするのはできそうでしたが、そうするとトラックパッドが使いにくい。
スナップショットは仮想マシンの状態を保存する重要な機能です。スナップショットを取ると、その時点の仮想マシンの状態が保存され、後でその状態に戻すことができます。これは、新しいソフトウェアを試したり、システム設定を変更したりする前に、システムの現在の状態を保存しておきたい場合などに便利です。しかし、現在のバージョンのParallels Desktopの仮想MacOSでは、このスナップショット機能は使用できないようです。

スナップショットは仮想環境を使う上で、期待している機能のひとつなので対応していないのは残念ですが、今後のアップデートで使えるようになることを期待します。
時間がズレるのはWindows環境ではそんなことなかったのですが、MacOSの仮想環境起動時にいつも時計がずれています。使っているうちになおるのですが。OSの時刻同期のタイミングなんですかね?
全体的な使い勝手
Parallels DesktopはWindowsにしても、MacOSにしてもパフォーマンス的には十分実用的です。
特にMac使いの人でときどきはWindowsが必要という人も場合は、Apple SiliconのMacでWindowsを使うほぼ唯一の選択になります。
機能も盛りだくさんで特に母艦側と仮想側の連携ではファイル共有機能や母艦側で仮想側のアプリを起動できる機能などが用意されていて便利ではあります。
ただ、連携がシームレスすぎてどっちを使ってるのか分からなくなってしまうこともあります。
僕の用途ではそういう連携機能は使わないようにして、各環境をなるべく独立して使う方が良いかなと思いました。
あと、もしかすると設定をうまくすれば使いやすくなるのかもしれませんが、仮想環境を使っている時でもショートカットキーに母艦側が反応してしまったりして混乱することがあります。
やっぱり、母艦の中で仮想環境が動いているというのは特殊な状態なので、普段使いでガッツリ使うにはコツや慣れが必要みたいで、何かの検証とかのために一時的に利用するような使い方が便利で良いと思います。
そういう意味では、Windowsマシンからリモードデスクトップで別なマシンに繋いで作業するのと似たような状態なのですが、リモードデスクトップは歴史が長いせいか最近は使っていてもあまり戸惑うことはないのですごいですね。
今回、Parallels Desktopの評価期間を利用してお試しで使ってみました。

Parallels Desktopの評価期間は2週間あるので、とりあえず使ってみてから購入するのが良いですね。
用途によっては買ってみても良いと思いますが、僕はMacの仮想環境のところに書いた問題点を許容できるかどうか検討してから購入を決めようと思ってます。

僕は仮想Mac OSでスナップショットとかの対応がされるまで待とうかな。
また、Parallels DesktopはMacOSのバージョンアップに合わせて毎年新バージョンが出ているようです。
買い方はサブスクリプションと買い切り版がありますが、買い切り版は将来のMacOSではサポート外になるはずなのでサブスクリプションの方が安心ではあります。
MacOSが新しくなると必ずしも古いParallels Desktopが使用できなくなるというわけではないので、どちらにするか悩ましいですね。
コスト的には、買い切り版を買って毎年アップデート版を買うのが一番安いかもしれないです。

今すぐ必要ではないなら、購入のタイミングはParallels Desktopの新バージョンが出た時が良さそうですね。
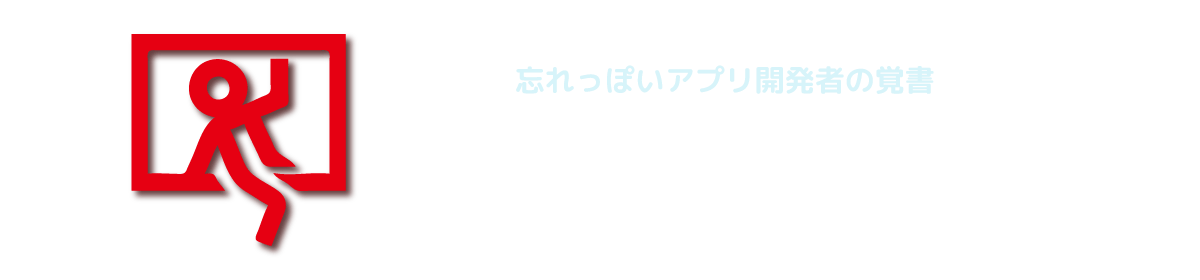


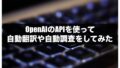

コメント